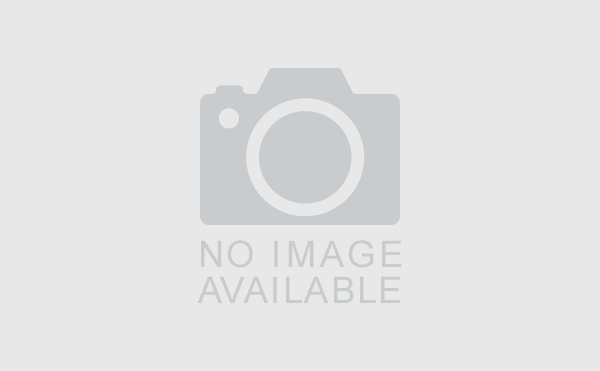最初に小学校、民生・児童委員(2例)、子ども・家庭支援センター、墨田児童相談所から5例の事例発表。その事例を受けた形で、医師会会長、歯科医師会会長、民生・児童委員、墨田児童相談所係長、子ども家庭支援センター所長の4人をパネラーに小学校校長がコーディネーター役でパネルディスカッションという進行プログラムでした。
民生・児童委員から、情報がないままでの見守りや、関わったケースへのフィードバックがないことが課題として挙げられたものの、シンポジウムは準備不足といった感が否めず、児童相談所のフィードバックに対する前向きな一言があっても、それを確実な手法にするための共有の会話にならず、ケースによって千差万別の対応をしなければならない虐待防止のためのケース会議を、現在どのように行っているのか、また、今回の事件の反省に立っての改善策をどのように構築したのか、その時の課題は何だったのか?といった具体的な話にもなりませんでした。
今回の事件の一番の問題は、子どもに直接会っていないこと、子どもの言葉をきちんと聴かないまま、事が進んでいってしまったことです。本来、家庭に入る権限は児童相談所にしかありません。その相談所が限られた人員で多くのケースを扱っていることが大もとの問題であることはわかりきっていたことであり、だからこそ、自治体単位で子どもや家庭の問題を支援する部署を置き、地域でていねいに一つ一つのケースに取り組むことでその問題を補うというのが、行政としてのマニュアルだったはずです。
シンポジウムの中で、子ども家庭支援センター所長が、「子どもの目線にたって問題にあたることが重要。まず、子どもの声を聴くことです。」と述べていたことが救いでした。